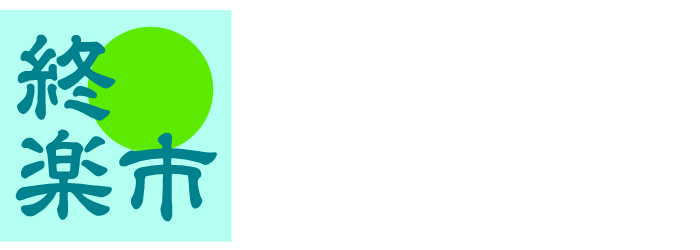故人様の年忌法要をお願いするお坊さんはおられますか?

故人様の年忌となる法要のタイミングにお坊さんをお手配いたします。
檀家に入られている方は三十三回忌まで行う方もいらっしゃいますが、そこまで信仰が深くなければ七回忌や十三回忌を目処に弔明けとする方が多いようです。命日を過ぎて行うことは良くないとされていますので、年忌の年はお早めに行動を起こされることをおススメします。
料金について
法事・法要僧侶派遣の基本料金
33,000円~
料金に含まれるもの
読経代
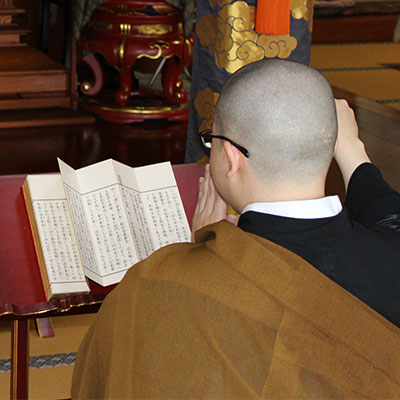
お布施

お膳料

お車代(交通費)

仲介手数料

オプション
宗派指定:+5,500円(税込)
※主要宗派対応可能
天台宗・真言宗・曹洞宗・臨済宗・浄土宗・浄土真宗本願寺派・真宗大谷派・日蓮宗など
法話の追加:+5,500円(税込)
読経の追加:+11,000円(税込)
※場所を移動しての供養の場合は、別途見積となります
供物(米酒塩)の用意:+5,500円(税込)
※お寺さんによって異なります
供養証明書:+5,500円(税込)
※寺院名と内容、日付け入りの証明書をメールで送付させて頂きます
写真 or 動画撮影: +5,500円(税込)
※撮影してもよいタイミングやアングルは、お寺さんのご指示に合わせていただきますようお願い致します
写真と動画をどちらもご希望の場合は、5,500円×2=11,000円となります。
四十九日法要について
ー位牌のご供養などの対応も可能ですー
33,000~58,300円
(宗派指定料:5,500円)
お客様が希望する内容によって料金が変わるのが四十九日法要です。
法要読経に加え、白木のお位牌の魂抜き供養、本位牌への魂入れ供養、魂が抜けて不要となった白木のお位牌のお焚き上げ供養を合わせたお値段が58,300円となります。
更に納骨供養も合わせて行いますと場所の移動と追加読経など追加費用が加算されますが、まとめて対応可能ですのでご相談ください。

ご依頼の多い法要
お問い合わせから完了までの流れ
2
内容のご確認・決定
弊社担当者がお客様とご相談の上、下記内容を決定させて頂きます。
- 日時
法事・法要を行いたい日時を第三希望くらいまでお決めください。(※命日を過ぎない日程でご予定下さい) - 法要の内容
四十九日・初盆・一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・墓前など何を行いたいのかをお伝えください。 - 手配する場所
ご自宅なのか、お墓なのか会場をお借りするのかによって手配場所が変わります。お寺法事の場合はお寺で行いたいとお伝えください。 - 宗派指定の有無
先祖代々から決められた宗派で執り行っているとわかっている場合はその宗派をご指定、特にこだわりがなければ指定しないとお伝えください。(宗派指定料:+5,500円)

3
寺院の手配
上記の条件を満たすお寺さんを提携先から当たります。
日時・場所OKのお寺さんが決まりましたらお客様へご案内いたします

4
調整・成立・お支払い
どうしても日時が合わない場合はお寺さんの都合に合わせて調整していただけないか、お客様にお願いする場合がございます。
調整がうまくいけば契約成立となり、依頼内容の詳細兼ご請求書をお送りしますので、お支払い期限までにお支払いください。

5
事前連絡
手配させていただいたお寺さんから事前にご挨拶のご連絡が入ります。その際に用意するものやご質問などありましたら直接お伺いください。
※依頼内容詳細にお寺さんの電話番号を記載しておりますので、その番号からの着信は対応いただけますようお願いします。

6
法務の実施
お坊さんが指定の日時・場所に伺い、祈祷を執り行います。
事前にお支払いいただいていますので当日の金銭のやり取りは一切ありません。

法要の種類といわれ
昔から亡くなった人は四十九日まではこの世にいて、その後成仏すると言われているように、四十九日法要は故人様が成仏するためにとても重要な法要です。また残された家族にとっても忌明けとなる節目の法要になります。
この四十九日法要でお位牌の魂の入れ替えを行い、ご遺骨をお墓に納骨することでいったんの区切りとする方が多いようですが、納骨は慌てる必要はなく、お気持ちの整理がついてからでも大丈夫ですので、四十九日法要までにすべきことをご準備ください。
本位牌は作りましたか? お墓への戒名彫りは終わりましたか? お坊さんは手配しましたか?
故人が亡くなってから初めて迎えるお盆に執り行う法要になります。四十九日よりも先に初盆の時期が来てしまう場合は、四十九日を過ぎてから最初に迎えるお盆となります。
お盆の時期は地域によって異なります。
旧暦:7月13~15日頃(首都圏・静岡県の一部・岐阜県の一部・沖縄など)
新暦:8月13~15日頃(北海道・東北・甲信越・東海・近畿・中国・四国・九州など全国的に)
一周忌法要とは、故人が亡くなってからちょうど1年後の祥月命日に行われる法要になります。
四十九日法要の次に大切な法要とされていますし、遺族にとっても大きな節目となる法要ですので親族や友人などを招いて大々的に行われることが多いです。
祥月命日が平日の場合は無理にその日にせず、多くの人に参列してもらうため前倒しで土日など集まりやすい日程で行うようにするといいでしょう。
回忌は亡くなった日を1と数えるため、三回忌は故人が亡くなった日から翌々年に執り行われます。
つまり、一周忌の翌年に三回忌を迎えるという流れになります。一番混乱するところですのでご注意ください。親族を招いて執り行うのが主流ですが、遺族だけで行う方も増えています。
故人が亡くなってから満6年目に行われる法要が七回忌法要、満12年目に行われるのが十三回忌法要です。本来ならば三十三回忌または五十回忌で弔い上げ(最後の法要)とし、それ以降の年忌法要は行わないのが慣例ですが、弊社にご依頼いただくお客様の多くは、この七回忌もしくは十三回忌を区切りと考え弔い上げとされる方が多いです。
弔い上げは、年忌法要の最後の法要として執り行われる法要の事をいい、一般的には三十三回忌や五十回忌をもって弔い上げとする方が多いです。弔い上げとなった故人様の魂は個としてではなく、今後、ご先祖様として祀られようになるため、お位牌の魂を個人のものから先祖代々のものへ入れ替える必要があります。
弔い上げの区切りはご遺族のお気持ち次第ですので、何回忌をもって終わりにしなければならないというわけではありません。
お寺法事・僧侶派遣のことなら何でもお気軽にご相談下さい