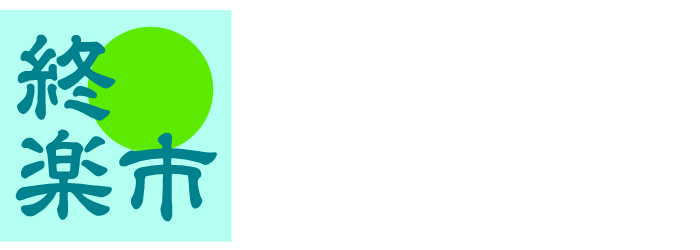浄土真宗本願寺派の歴史と教え
浄土真宗本願寺派(じょうどしんしゅう ほんがんじは)は、日本の仏教の一宗派で、浄土真宗(じょうどしんしゅう)の主要な分派の一つです。
本山は京都市にある西本願寺(正式名称:龍谷山 本願寺)で、全国に多くの門徒を擁しています。
開祖は親鸞(しんらん、1173年~1263年)で、法然(ほうねん)の弟子として阿弥陀仏の本願を説き「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」の念仏を称えることで救われるという「他力本願」の教えを強調しました。
修行や戒律ではなく、信心を重視し、日常生活の中で仏の教えを生きることを大切にしています。
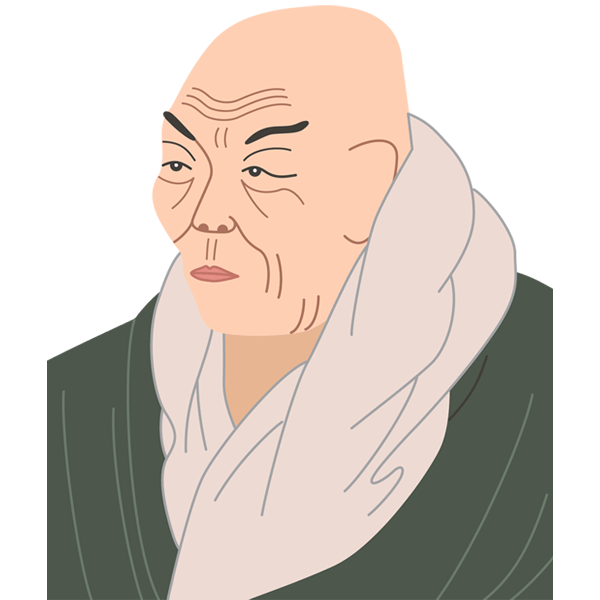
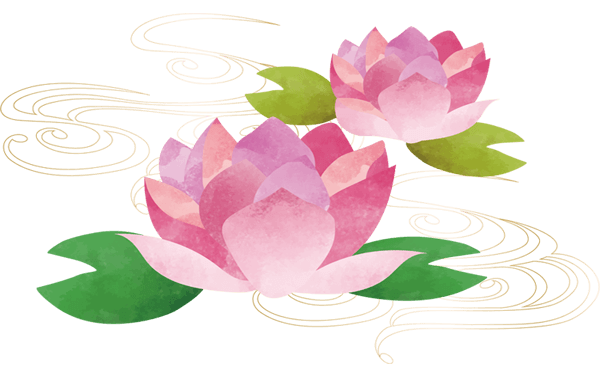
浄土真宗本願寺派の特徴
①絶対他力の教え
②称名念仏(南無阿弥陀仏)
③開祖・親鸞聖人の教え
④僧侶の結婚が認められる
⑤宗派のシンボル「阿弥陀如来」
⑥厳しい戒律がない
⑦葬儀や法要の特徴
⑧本山「西本願寺」
浄土真宗本願寺派が多い地域
浄土真宗本願寺派(西本願寺派)が多い地域として、近畿地方(京都府・滋賀県)、北陸地方(富山県・石川県・福井県)、東海地方(愛知県・岐阜県)、近畿・中国地方(大阪府・兵庫県・広島県)、九州地方(福岡県・熊本県)があげられます。
特に、北陸地方(富山・石川・福井)は「真宗王国」とも呼ばれるほど信仰が厚い地域で、東海や近畿地方も本願寺派の影響が強いです。

浄土真宗本願寺派の作法
お焼香

焼香は「一回」のみで頭(額)に押し頂かず、そのまま香炉に入れます。合掌・礼拝を大切にすることが重要です。
手順は
①焼香をする前に、まず合掌して一礼。
②額に押し頂かず、右手の親指・人差し指・中指で抹香(粉状の香)をつまみ、そのまま香炉に入れます。
③焼香が終わったら、再び合掌して礼拝します。
④静かに席へ戻ります。
数珠

浄土真宗本願寺派の数珠は、他の宗派と異なる特徴があります。一般的に「単念珠(たんねんじゅ)」を使用し、108個の珠が連なる正式な念珠ではなく、片手用の略式数珠を用いることが多いです。
「梵天房(ぼんてんふさ)」と呼ばれる丸いふさがついたものが特徴的ですが、普通の房でも問題ありません。
使い方は念珠を合掌の際に手にかけるか、手に持って合掌します。
戒名

浄土真宗本願寺派の戒名(法名)は、他の宗派の「戒名」と異なり、「法名(ほうみょう)」と呼ばれます。
「釋(しゃく)」または「釋尼(しゃくに)」の字がつくのが特徴です。
基本的に「居士(こじ)」や「大姉(たいし)」はつけず、特別な場合に「院号」がつくことがあります。