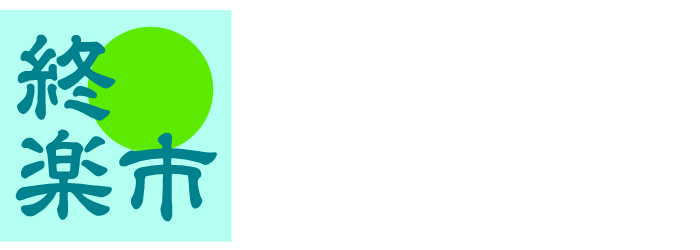曹洞宗の起源
曹洞宗(そうとうしゅう)は、禅宗の一派であり、中国の唐代に洞山良价(どうざんりょうかい)と曹山本寂(そうざんほんじゃく)によって確立されました。
日本での歴史と特徴
日本では、鎌倉時代に道元(どうげん)禅師と瑩山(けいざん)禅師によって日本に伝えられました。大本山は、福井県の永平寺と神奈川県の總持寺です。
教えの特徴として、
- ①最も重要な修行は「只管打坐」、すなわち「ひたすら坐禅をする」
:悟りを開くために坐禅をするのではなく、坐禅そのものが悟りの実践であると考えます。 - ②「修行」と「悟り」は別のものではなく、一体である
:特別な悟りの体験を求めるのではなく、日々の修行を大切にします。 - ③坐禅を通じて自我を超え、仏の境地に至ることを説いています。
- ④坐禅だけでなく、日常の行い(食事、掃除、仕事など)もすべて修行の一環と考えます。
- ⑤誰もがそのままで仏になれる可能性を持っている
:特別な修行や悟りを求める必要はなく、すでに仏道を歩んでいるという立場です。 - ⑥曹洞宗の教えの根本には、道元禅師の著作『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』があります。
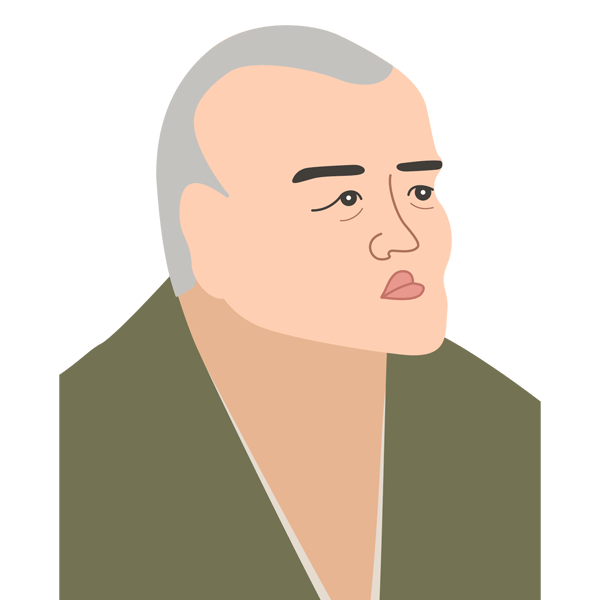
曹洞宗が多い地域
曹洞宗の寺院が多い地域として、曹洞宗の大本山の一つ「永平寺」がある福井県、もう一つの大本山「總持寺」がある神奈川県、石川県、東北地方(特に岩手県・山形県)、新潟県・長野県などです。

曹洞宗の作法
お焼香

焼香の仕方は、
- 仏像や位牌など、対象者に向かって合掌礼拝をする
- 焼香台に置かれた香炉に近づき、右手の浄指(親指、人差指、中指)で香を1つつまむ
- 左手を右手の下に添えて、額に軽く押し当てる
- 「焼香は2度」1度目は額に手を持っていき、2度目はそのまま
※会葬者が多い際には「焼香は1回で」と指示されることもあります。 - 対象者に向かって合掌礼拝をし、数珠を両手にかけて合掌・礼拝をする。
数珠

曹洞宗の数珠は、基本的に108個の珠を持つのが一般的ですが、禅宗ではその数にこだわりが少なく、数珠はあくまでも修行や禅の心を深めるための道具として使われます。
数珠を使い心を静め、仏の教えを思い起こすことが目的です。
戒名

戒名は、仏教徒が出家して仏道を歩む際に与えられる名前です。
戒名には、仏教の教義に基づいた意味が込められており、通常は「法号」とも呼ばれます。過度に華やかではなく、質素で謙虚な名付けがされる傾向があります。