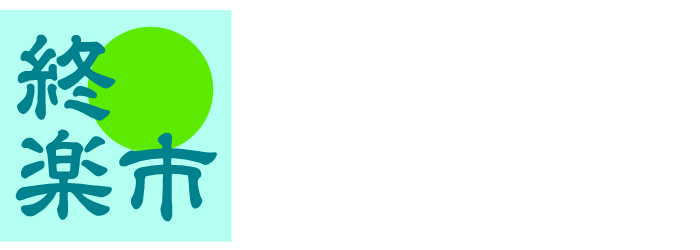浄土宗の歴史
浄土宗(じょうどしゅう)は、日本の仏教の一宗派で、法然(ほうねん)(1133年~1212年)によって1175年に開かれました。
阿弥陀仏(あみだぶつ)を信じ、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と念仏を称えることで、極楽浄土に往生し誰でも救われるという平等な教えが特徴です。
法然は、「修行や学問よりも、ただひたすら念仏を唱えることが重要」と説き、これを「専修念仏(せんじゅねんぶつ)」といいます。律儀な修行や難しい経典の理解が必要とされないため、武士や庶民にも広まりました。
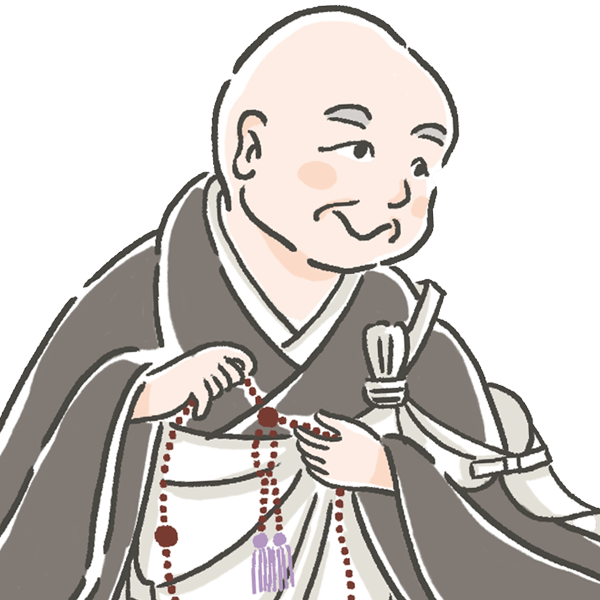
浄土宗の教えと特徴
浄土宗の教えとして
①他力本願:自力での修行よりも、阿弥陀仏の力にすがることで救われる
②六字名号:「南無阿弥陀仏」の六字が浄土宗の根本的な教え
③極楽浄土:念仏を唱えた人は死後、阿弥陀仏のいる極楽浄土に生まれ変わる
とされています。
修行は、厳しい苦行ではなく「念仏」を中心とした信仰の実践が基本です。日々の生活の中で、念仏を称え、善行を積むことで修行が成り立つのが特徴です。
禅宗や天台宗が坐禅や学問を重視するのに対し、浄土宗は「念仏一つで極楽往生できる」というシンプルな教えを持ちます。
親鸞が開いた浄土真宗は、浄土宗と似ていますが、「阿弥陀仏の力を完全に信じれば念仏を唱えなくても救われる」とする点で異なります。
浄土宗が多い地域
総本山は京都の知恩院で、代表的な寺院として、増上寺(東京)・光明寺(鎌倉)があります。
寺院が多い地域として、近畿地方(京都府・滋賀県)・関東地方(東京都・神奈川県・千葉県)・東海地方(愛知県・静岡県)・九州地方(長崎県・福岡県)があります。
特に関西を中心に、江戸時代の寺院政策の影響で全国に広まった経緯があります。

浄土宗の作法
お焼香

焼香の作法として、香は仏に供えるものと考えられているため、額にいただかずにそのまま香炉に入れるのが特徴です。
①礼拝(祭壇や位牌に向かい合掌・一礼)
②焼香(一般的には3回、地域や寺院によって異なります)
③合掌・念仏(胸の前で両手を合わせ合掌、心の中で「南無阿弥陀仏」と唱える)
④礼拝(合掌・一礼)
の手順です。
数珠

浄土宗の数珠(念珠)は、一般的に 108玉の念珠を使用し、念仏を唱える際に用いられます。特徴として主玉(しゅぎょく)、親玉(おやだま)、四天玉(してんだま)、頭房(かしらつきふさ)でできています。
戒名

浄土宗の戒名は「院号(いんごう)・道号(どうごう)・戒名(かいみょう)・法号(ほうごう)」 で構成されます。