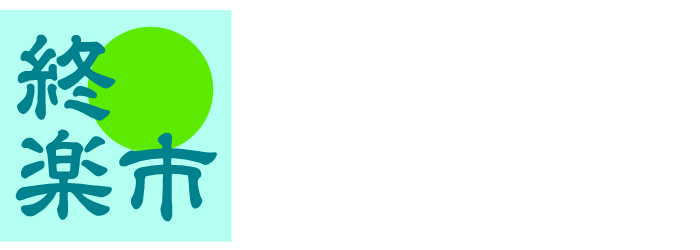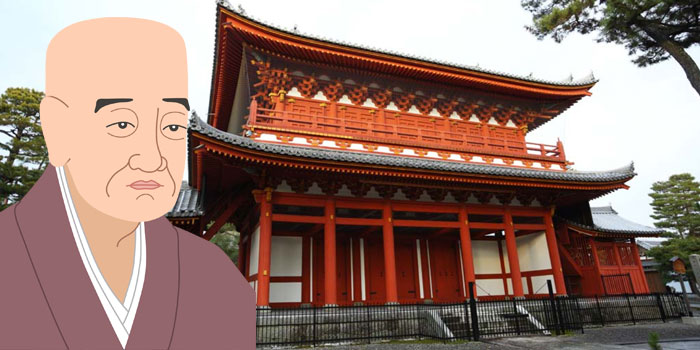臨済宗の起源と特徴
臨済宗(りんざいしゅう)は、禅宗の一派で、中国の唐代に臨済義玄(りんざい ぎげん)によって開かれた仏教の宗派です。
主に禅の修行を通じて、悟り(覚り)に至ることを目的としています。唱えるお経は「南無釈迦牟尼仏」です。
特徴として、
①師匠が弟子に対し、答えのない難題(公案)を与え、考え抜くことで悟りへ導く
②師匠が弟子を激しく指導する「棒喝(ぼうかつ)」(棒で打つ、怒鳴る)を行う
などがあります。
日本での歴史
日本では、鎌倉時代に栄西(えいさい/ようさい)が宋から伝え、鎌倉幕府や武士階級に支持されました。
現在の日本の臨済宗は、妙心寺(みょうしんじ)、建仁寺(けんにんじ)、南禅寺(なんぜんじ)、円覚寺(えんがくじ)、建長寺(けんちょうじ)など14本山(大きな寺院)を中心に展開されています。
武士道と深く結びつき、精神鍛錬の手法として取り入れられ、茶道や芸術(禅画、庭園、書道)にも大きな影響を与えました。
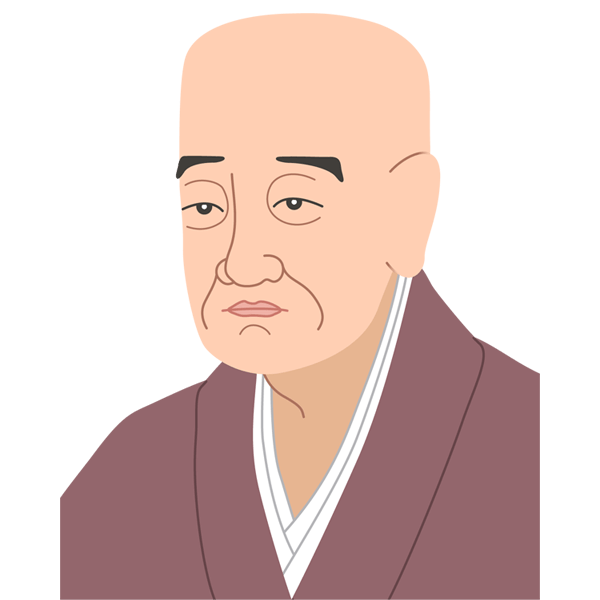
臨済宗が多い地域
臨済宗の多い地域は、日本の歴史や文化の影響を受けた場所に多く見られます。
特に京都府・鎌倉(神奈川県)・愛知県・福岡県・静岡県などの地域に多くの臨済宗の寺院が存在します。

臨済宗の作法
お焼香

焼香の仕方は、
①焼香台の前に進み、遺影や本尊に向かって合掌し、一礼
②右手の親指・人差し指・中指の三本で抹香をつまみ、つまんだ抹香をそのまま香炉にくべます(頭にかざさない)
③焼香を終えたら、静かに合掌
④遺影や本尊に向かって軽く一礼し、
その後、僧侶や喪主に対しても軽く一礼して席に戻ります。
数珠

臨済宗の数珠は、基本的に略式数珠(片手数珠)と本式数珠(正式数珠)の2種類があります。
略式数珠は、一般的に108玉ではなく、少ない数の玉で作られています。(22玉、27玉などが多い)一連のシンプルな形で、宗派を問わず使用できます。
本式数珠は108玉(または半分の54玉)で構成されます。
親玉1つ、主玉108個、四天玉4個、房(ふさ)がついています。
使い方としては、数珠を左手にかけて合掌し、念仏や読経の際に用います。
戒名

戒名の特徴として、「○○居士」「○○大姉」などの位号がつき、社会的に貢献した人や寺院と縁が深い人には「院号」や「禅定門・禅定尼」などがつくこともあります。
「道号」「戒名」「位号」の3つで構成され、僧侶から授かります。