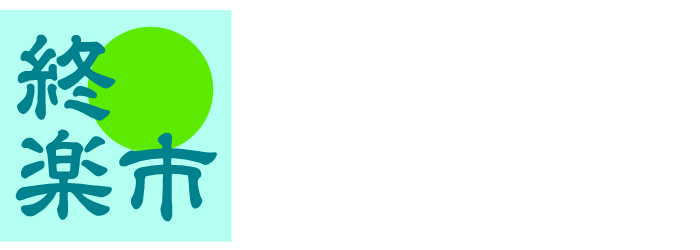真言宗の歴史と特徴
真言宗(しんごんしゅう)は、日本の仏教の一派で、平安時代の僧・空海(弘法大師)によって開かれた密教の宗派です。
インドや中国から伝わった大乗仏教の教えを基にし、「即身成仏(そくしんじょうぶつ)」の思想を重視します。これは、生きたまま悟りを開き、仏となることが可能であるという考え方です。
代表的な経典は『大日経』『金剛頂経』です。真言宗では大日如来を宇宙の根本仏とし、あらゆるものの本質と考えます。
また真言宗では、「身・口・意」の三つの行動を通じて修行を行います。「胎蔵界曼荼羅」と「金剛界曼荼羅」の二つの曼荼羅(まんだら)を使用し、願いを仏に届ける護摩(ごま)焚きなどの修法などが特徴です。
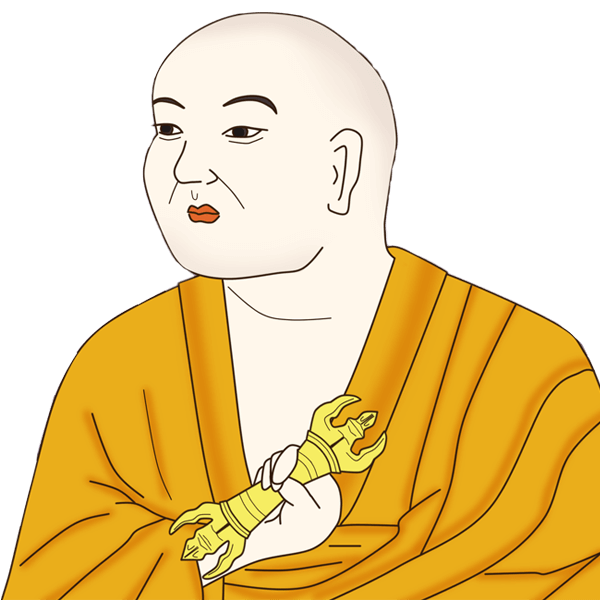
真言宗の教えと宗派
真言宗は「密教」と呼ばれ、一般の人には公開されない秘密の教えが多くあります。師から弟子へと口伝で伝えられ、特定の儀式や修行を通じて悟りに近づくことを目的とします。
真言宗の教えは、深遠で実践的なものが多く、現代でも多くの人に影響を与えています。
現在、日本には様々な真言宗の宗派があり、大きく「高野山真言宗」「東寺真言宗」「真言宗豊山派」「真言宗智山派」などに分かれています。
各宗派で教えや修行のスタイルが異なるものの、基本的な密教の教えは共通しています。
出家しなくても実践できる修行として、
①写経(しゃきょう):「般若心経」や「大日経」などを写す修行
②念誦(ねんじゅ) :「南無大師遍照金剛」や「光明真言」などを唱える
③阿字観:簡易的な瞑想を行う
④ 護摩祈願:寺院で護摩供養に参加する
などがあります。
真言宗が多い地域
真言宗の寺院が多い地域として、四国地方(特に高野山と関係の深い地域)、近畿地方(特に奈良・京都・大阪)、関東地方(特に鎌倉・東京)、中国・九州地方が挙げられます。
主要寺院として高野山金剛峯寺(和歌山県)・東寺(教王護国寺・京都)・成田山新勝寺(千葉県)・川崎大師(神奈川県)があります。

真言宗の作法
お焼香

真言宗のお葬式での焼香は3回です。
焼香台の前に進み、遺族に一礼、焼香台の前で合掌、一礼、右手の人差し指と中指、親指の3本で抹香をつまんで、額の高さまであげてから香炉に置きます。
これを3回繰り返した後に合掌、焼香台から下がり、遺族に一礼をします。
数珠

真言宗の数珠(念珠)は、主に 108珠 で構成される正式なものが多いですが、略式のものもあります。
特徴として主玉(しゅぎょく)、親玉(おやだま)、四天玉(してんだま)、弟子玉(でしだま)、房(ふさ)でできています。
戒名

真言宗の戒名(法名)は、通常 「院号(いんごう)・道号(どうごう)・法号(ほうごう)」 の3つで構成されます。
格式によって「院号」が省略される場合もあります。